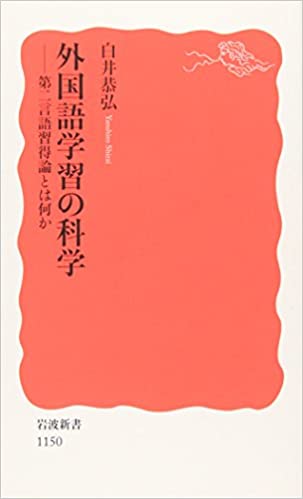山岡政紀 書評集
書評『外国語学習の科学──第二言語習得論とは何か』 白井恭弘著/岩波新書/2008年9月19日 発行/定価700円/ISBN 978-4-00-431150-8
日本では中学・高校で外国語が必修となっていて、多くの生徒は英語を学習する。大学では、通常二つ以上の外国語を学ぶ。日本人の多くが外国語学習を肌で体験している。そしてその誰もが、外国語学習に困難やストレスを感じたり、効率的な方法を試行錯誤したりしている。より優れた外国語学習法は何か──誰もが知りたいそのことを探究する学問分野が「第二言語習得論」(Second
Language Acquisition)だ。第一言語とは幼少時に無意識に獲得される母語を指し、第二言語とは母語獲得後に意識的に学習して習得される言語のことである。
第二言語習得論は学際的分野で、心理学、言語学、教育学、社会学など、広い学問領域に関わっているが、基盤となっているのは経験科学としての心理学である。つまり、心の中のことを主観的に分析するのではなく、調査によって蓋然性のあるデータを取得し、統計処理を用いてデータ解析を行うという現代心理学の一般的な手法が採られている。この第二言語習得論という分野ではどのようなテーマで研究が行われているのか、そして、それは外国語学習者である一般読者に何か有益な情報を提供できるものかといったことを、平易な文章で解説してくれているのが本書である。
第1章「母語を基礎に外国語は習得される」は第二言語学習における母語と目標言語との言語間距離がテーマだ。英語話者にとって同じインド・ヨーロッパ語族のドイツ語、フランス語、スペイン語は距離が近く、習得しやすいのに対し、距離の隔たった日本語、中国語、アラビア語などは習得に倍以上の時間がかかるというデータが示されている。日本語と韓国語の言語間距離が近いことは両言語の文法構造や語順の近親性からも直観的にわかるが、学習時間と到達レベルの相関関係からも相互の習得しやすさが証明されている。言語間距離の近い言語は習得しやすい反面、その近さゆえに母語の影響を強く受ける傾向にある。第1章後半は、言語転移と呼ばれるこの現象について重点的に説明している。さらに文化的な影響によって生じる語用論的転移という現象もある。例えば、日本語では自分で見つけたのに「財布がみつかった」と言ったり、借りた物を壊してしまったときに「ごめん、テレビが壊れちゃった」と言ったりなど、他動的行為を自動詞で表現することが多いのは日本語の文化的特徴であり、学習者には習得しにくいとされる。今日においては認知言語学の領域で議論されるトピックでもある。
第2章「なぜ子どもはことばが習得できるのか――臨界期仮説を考える」では、言語習得と学習開始年齢の相関関係をめぐる諸理論が紹介されている。幼児期の母語習得はたいてい成功するのに、大人になってからの第二言語習得はなかなかうまくいかないことは経験的によく知られている。そのため、ある年齢を過ぎると言語学習が不可能となる臨界期が存在すると考える「臨界期仮説」が根強くある。ここでは、この仮説に対してこれまでに行われてきた脳神経学的な考察、認知的な考察、環境の変化を学習困難の主因と見る考察、母語の習得が第二言語習得を妨げるとする考察など、多様な説が紹介されている。トータルに見て臨界期仮説を論証するよりは反証する説、つまり年齢とは別の要因が第二言語習得を遅らせるとするものが多いようである。
第3章「どんな学習者が外国語学習に成功するか――個人差と動機づけの問題」では、外国語学習の個人差がテーマだ。つまり、外国語学習というのは人によって向き不向きがあるのか、あるとすればその人のどのような特性が外国語学習への適性となるのかについての、興味深い考察が紹介されている。例えば、知能指数(IQ)との相関関係を調査した研究があるが、結果は重なる部分はあるものの本質的には一致しないらしい。つまり、知能指数が高くても語学に向かない、逆に知能指数が低くても語学が得意という人は多くいるわけだ。成人してから始めた語学がネイティブ並みのレベルに到達した事例を集中的に調査した研究もあり、それによるとそうした成功例に共通するのは①音声認識能力、②言語分析能力、③記憶力の三つだという。また、学習への動機づけを語学習得の主要因とする考察もある。学習対象言語への共感や好意的評価を持った人は、その文化の一員として参加したいという動機づけが高まり、語学習得が成功することが多いという。
第4章「外国語学習のメカニズム――言語はルールでは割り切れない」では、外国語ができるようになるとはどういうことか、そのプロセスに関する考察が紹介されている。単に単語や文法を知っているだけではだめで、音声の体系も知らなければならないし、言語を用いて適切な対人関係が構築できる社会言語能力も不可欠であることが指摘されている。幼児期の母語習得は専ら聴くことのみから始まることから、言語は聴くこと・読むことを通じて言語内容を理解することによって習得されるとする「インプット仮説」がある。もしそれが正しければ、話すこと・書くことのアウトプットは言語学習に必要ないことになる。しかし多くの研究はこの仮説を否定し、第二言語習得にはアウトプットも必要であると考察している。
第5章「外国語を身につけるために――第二言語習得論の成果をどう生かすか」では、言語教育で実践されているオーディオ・リンガル法やコミュニカティブ・アプローチといった教授法を取り上げ、第二言語習得理論の観点から各教授法の特性を論評している。
第6章「効果的な外国語学習法」では、最後に外国語学習の効果的学習法について述べている。本書でこれまでに言及してきたおびただしい研究群の成果をまとめたものであると同時に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で修士号と博士号を取得した筆者自身が、英語を習得した経験を踏まえた実践的な学習法が具体的に記されている。その詳細は直接本書を読んでいただいたほうがよいと思うが、その一端だけ紹介すると、聴解・読解のインプットは背景知識が重要となるので、なるべく興味があってよく知っている分野のものをインプットするのがよいと言う。そう言えば私も大学受験のときの英語長文読解の練習では大好きな音楽関係の文章を重点的に読んで読解力が向上した思い出がある。また、20%しか理解できない教材より80%理解できる教材を何度も聴くほうが、効果があるといった具体的な内容が記されているので、第二言語習得理論に興味がなくても語学習得を目指したい読者ならば、第6章だけでも読めばよいのではないかと思う。
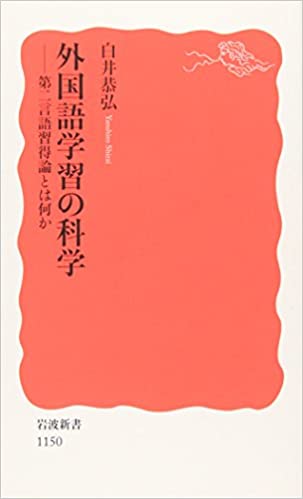
創価大学ホームページ へ
山岡ホームページへ